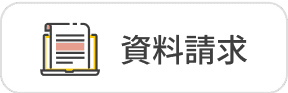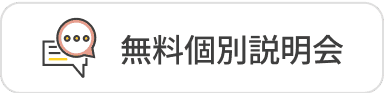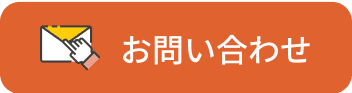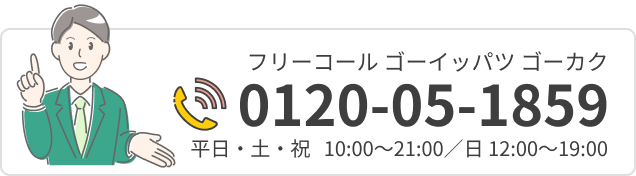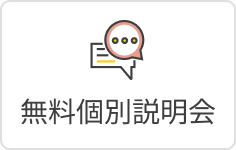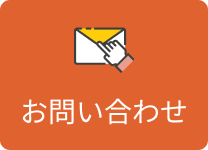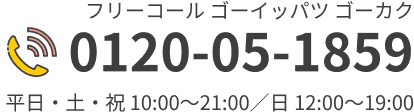newsロバみみ広場
アレコレつまみぐい国語-古典文法マスターへの道①-
「なり」の識別
識別は文法の最終仕上げです。入試で問われる文法問題はこの識別にかかっています。しっかり押さえておきましょう。今日はまず「なり」の識別を紹介します。
1.終止形(ラ変は連体形)+なり→伝聞推定の助動詞「なり」
2.連体形・体言+なり→断定の助動詞
3.物の性質・状態+なり→形容動詞ナリ活用の活用語尾
4.~と・~に・~く・~ず+なり→ラ行四段活用の動詞「成る」の連用形
しかし、1.と2.の区別が、四段・上一・下一・ラ変型の活用をする言葉に接続する場合は、活用形だけでは判断できません。
なぜなら、四段・上一・下一の動詞は、終止形・連体形が同形で、終止形接続の「伝聞推定」のなりもラ変型のみ連体形接続だからです。
◎四段・上一・下一・ラ行変格活用に接続している場合の判断方法
まず、音便化をしているかどうかチェックをします。
あんなり(あなり)・なんなり(ななり)・ざんなり(ざなり)
このような形になっている場合、なりは「伝聞推定」のなりです。「あんなり」はラ変型の動詞「あり」の連体形「ある」とくっついて「ある+なり」となり、さらに「る」が撥音便化し、「あんなり」となったものです。よって、なんなりは「なるなり」、ざんなりは「ざるなり」が音便化したものになります。
終止形接続の助動詞がラ変型の活用をする言葉に接続すると、撥音便化・無音便化が発生します。
次に、文章の表現を見てみましょう。
人の声や物音、笛の音などのワードが文中にあると、これも「伝聞推定」のなりです。
なぜなら、伝聞推定のなりはもともと「音あり(ねあり)」から変形してできた言葉で、聴覚的根拠をもとに推定する助動詞だからです。
この2つで判断できない場合は、主語を見てみましょう。主語が一人称「私」であれば、「断定」のなりです。自分自身のことについて聴覚的に推定することはまずないでしょう。
最後に、下に「けり」や「む」のような未然形・連用形接続の助動詞がつく場合、(なりけり・ならむ)「なり」は「断定」のなりです。「伝聞推定」のなりの活用表を見てみましょう。
未然 連用 終止 連体 已然 命令
なり| 〇 (なり) なり なる なる 〇
このように、「伝聞推定」のなりは未然形がなく、連用形も使われません。
まとめると
撥音便化・無音便化している→伝聞推定のなり
音に関係した表現がある→伝聞推定のなり
主語が一人称→断定のなり
下に未然形・連用形接続の助動詞がある→断定のなり
まずは冒頭の4つの判断をマスターすることが大事ですが、1.と2.で迷った場合はこの公式を使ってみてください。



access 交通アクセス
access 交通アクセス
神泉駅(京王井の頭線)より徒歩2分
渋谷駅(JR各線、田園都市線、半蔵門線、銀座線、東横線、井の頭線)
より徒歩5分、渋谷マークシティ道玄坂出口より徒歩1分
渋谷マークシティ ウエストモール4F(レストランアベニュー)を通り、マークシティ「道玄坂出口」を出ます。
正面の「道玄坂上交番前」交差点の信号を渡り、左手へ上ります。
「道玄坂上交番」の前を過ぎ、20mほど進むと1Fに玉川屋呉服店がございます。そのビルの7Fがapsアカデミーです。
〒150-0044
東京都渋谷区円山町5-3 玉川屋ビル7F