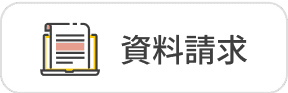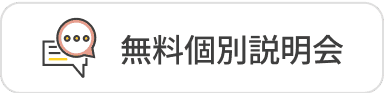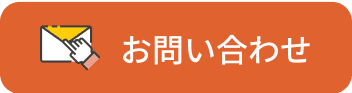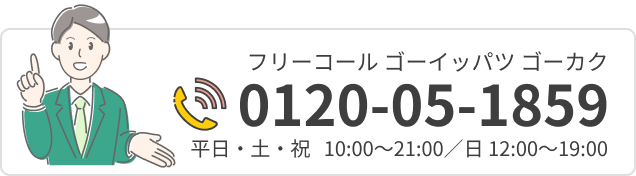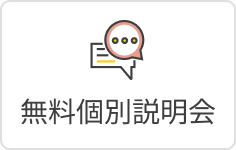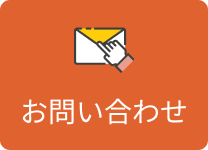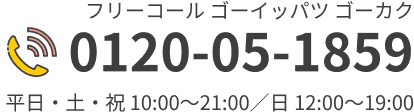newsロバみみ広場
アレコレつまみぐい国語-古典文法マスターへの道⑦-
「この児さだめておどろかさむずらむ」
この文章をどうやって品詞分解しますか?先日生徒さんが品詞分解したのはこうでした。
この/児/さだめ/て/おどらかさ/む/ず/らむ
この【連語】:代名詞「こ」+格助詞「の」
児【名詞】:「ちご」と読む。赤ん坊・子供の意。
さだめ【動詞】:定む(下二段活用)の連用形。
て【接続助詞】:連用形接続の助詞。「~て」と文章を繋げる。
おどろかさ【動詞】:おどろかす(四段活用)の未然形。びっくりさせる・起こす・気付かせるの意。
以下は「む【推量の助動詞】+ず【打消の助動詞】+らむ【現在推量の助動詞】」
このような構成になりますが、後半に何か違和感がありませんか?
「む/ず/らむ」
間に挟まれた「ず」。助動詞「ず」の活用は二段に分かれています。
未然 連用 終止 連体 已然 命令
ず | ず ず ず ぬ ね 〇
|ざら ざり 〇 ざる ざれ ざれ
それは何故かご存知でしょうか。「ず」は、下にさらに助動詞がくっつく場合は「ざら・ざり…」の活用の方を使用するのです。
そうすると、「ず」の下に助動詞の「らむ」が来るという形は成り立たないはずです。「ず」が「らむ」の上にくるのなら、このような形になります。
「ざるらむ」
さらに、ずの上に助動詞「む」が来ることもありません。もし「ず」と「む」がくっつくとしたらこうなります。
「ざらむ」
よって、「む/ず/らむ」という分解は不可能ということになります。正しくは「むず/らむ」。
助動詞「ず」は助動詞の中で現代でも馴染みのあるもので目に入りやすいですが、文法には規則があり、それに従って文章は作られています。きちんと論理を考えて判断していきましょう。「むず」の「む」と「ず」を離して考えないように。
次回は「むず」の下に来ている「らむ」の識別を行ないます。



access 交通アクセス
access 交通アクセス
神泉駅(京王井の頭線)より徒歩2分
渋谷駅(JR各線、田園都市線、半蔵門線、銀座線、東横線、井の頭線)
より徒歩5分、渋谷マークシティ道玄坂出口より徒歩1分
渋谷マークシティ ウエストモール4F(レストランアベニュー)を通り、マークシティ「道玄坂出口」を出ます。
正面の「道玄坂上交番前」交差点の信号を渡り、左手へ上ります。
「道玄坂上交番」の前を過ぎ、20mほど進むと1Fに玉川屋呉服店がございます。そのビルの7Fがapsアカデミーです。
〒150-0044
東京都渋谷区円山町5-3 玉川屋ビル7F