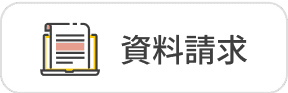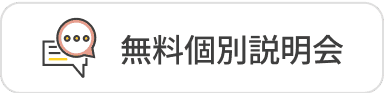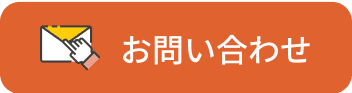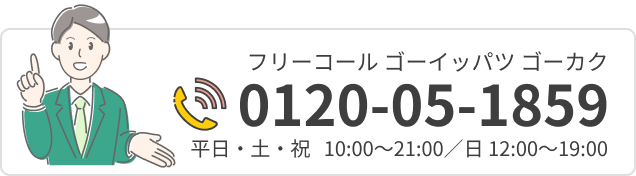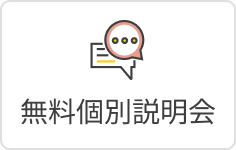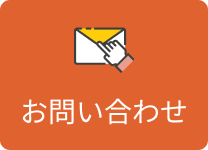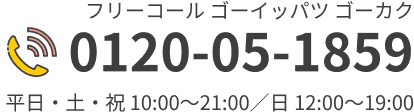newsロバみみ広場
アレコレつまみ食い国語-古典文法マスターへの道⑨-
助動詞には複数の意味があります。このような場合、どの意味をあてはめればよいのかという目安として、公式が存在します。
例えば助動詞「る」の場合、①可能②尊敬③自発④受身の4種類の意味を持っていますが、判断として
可能…打消を伴う場合(ず・なし・じetc)
尊敬…主語が貴人、もしくは上に尊敬語を伴う場合
自発…上に心情語(思ふ、偲ぶ・かなし)・知覚語(知る・聞く・見る)が来る場合
受身…「~に」という受身の対象がいる場合
という目安が公式として利用されています。
しかし、この公式が一文で複数出てきた場合、どう判断するべきでしょうか?
(例)まろあれば、さやうのものにはおどされじ。
この一文には「~に(は)」という受身の対象と、「じ」という打消推量の助動詞の両方があります。さて、この文の「れ」は1.で訳すべきなのか、4.で訳すべきなのかということになりますが、判別は簡単です。
上から読んで、先に来ている公式を優先します。
よって、訳は
「私がいるので、そのような者には脅されまい。」
というように、受身での訳になります。
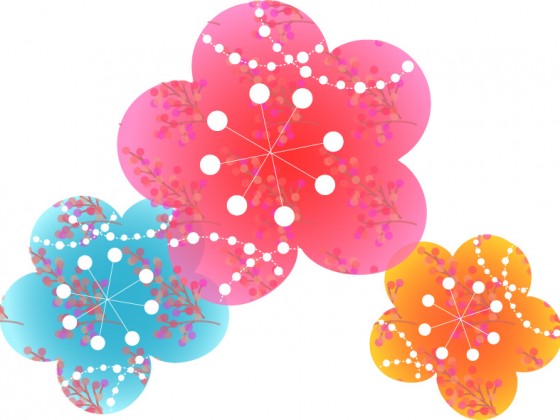



access 交通アクセス
access 交通アクセス
神泉駅(京王井の頭線)より徒歩2分
渋谷駅(JR各線、田園都市線、半蔵門線、銀座線、東横線、井の頭線)
より徒歩5分、渋谷マークシティ道玄坂出口より徒歩1分
渋谷マークシティ ウエストモール4F(レストランアベニュー)を通り、マークシティ「道玄坂出口」を出ます。
正面の「道玄坂上交番前」交差点の信号を渡り、左手へ上ります。
「道玄坂上交番」の前を過ぎ、20mほど進むと1Fに玉川屋呉服店がございます。そのビルの7Fがapsアカデミーです。
〒150-0044
東京都渋谷区円山町5-3 玉川屋ビル7F