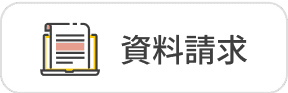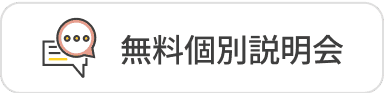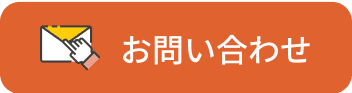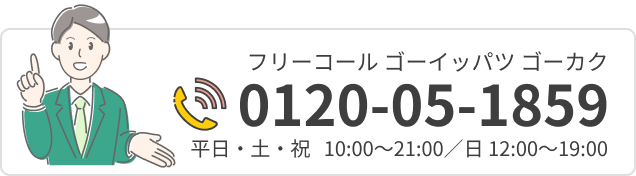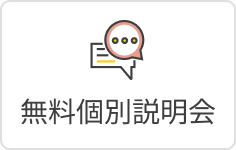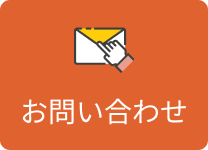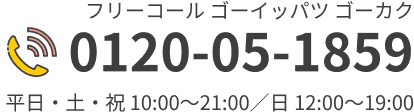newsロバみみ広場
センター試験廃止&新テストについて(3)
~「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」は複数回受検が可能(後編)~
気になるのは「合教科・科目型」「総合型」の問題とはいったいどんなものなのか・・・ということです。答申では「教科を越える思考力・判断力・表現力」の例として、次のことを挙げています。(前回のつづき)
求められる「力」
・言語に関する力
・数に関する力
・科学に関する力
・社会に関する力
・問題発見・解決力
・情報活用能力
またこれらから結び付けられる教科・科目について挙げています。
・言語に関する力 →国語・英語(読解力、要約力、表現力、コミュニケーションなど)
・数に関する力 →数学(統計的思考力、論理的思考力、図やグラフを描いたり読んだりする力など)
・科学に関する力 →理科(モデルをつくって説明する力、計画をたてる力、抽象化する力、大雑把に推定する力など)
・社会に関する力 →地歴または公民(合理的思考力、歴史や社会の問題を特定し、議論の焦点を定める力、矛盾点をあらわにする力など)
・問題発見・解決力 →総合および各教科・科目(答えのない問題に答えを見いだす力、問題の構造を定義する力、問題解決の道筋を文脈に応じて定める力など)
・情報活用能力 →情報(情報を収集する力、情報を整理する力、情報を表現する力、情報を的確に伝達する力など)
**********************************************************************
答申では、「例えば、言語に「関する力を主に育成する国語・英語を、他教科(例えば理科)と組み合わせ、理科の文脈の中で言語に関する「思考力・判断力・表現力」を評価する問いを作問する」としています。
「合教科・科目型」「総合型」の問題については今後早急に検討を進めるとしていますが、その参考となるものとして、次のようなものを挙げています。実際の問題がどのようになるかを予想する手がかりになるものと思われています。
・全国学力・学習状況調査の主として「活用」に関する問題
・文部科学省が実施している情報活用力調査
・各大学の個別選抜における総合問題・小論文
・高等学校の総合的な学習の時間における課題
・大学入試センター試験における「新しい試験の開発に関する研究」など
**********************************************************************
>>>check!<<<
「年複数回実施」の具体的な実施回数や実施時期については今後、協議されますが、「入学希望者が他者からの指導に受動的に従うのではなく、自ら考え自ら挑戦できるようにすることを第一義として」とされています。
注目すべきは「資格試験的利用を促進する」という部分でしょう。点数ではなく「段階別表示」とされているため、例えば、大学の個別選抜の受験資格に「大学入学希望者学力評価テストの評価がAの者」といった条件がつくことが想定されます。
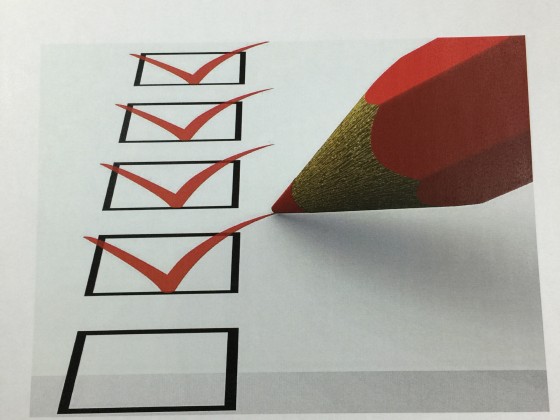



access 交通アクセス
access 交通アクセス
神泉駅(京王井の頭線)より徒歩2分
渋谷駅(JR各線、田園都市線、半蔵門線、銀座線、東横線、井の頭線)
より徒歩5分、渋谷マークシティ道玄坂出口より徒歩1分
渋谷マークシティ ウエストモール4F(レストランアベニュー)を通り、マークシティ「道玄坂出口」を出ます。
正面の「道玄坂上交番前」交差点の信号を渡り、左手へ上ります。
「道玄坂上交番」の前を過ぎ、20mほど進むと1Fに玉川屋呉服店がございます。そのビルの7Fがapsアカデミーです。
〒150-0044
東京都渋谷区円山町5-3 玉川屋ビル7F