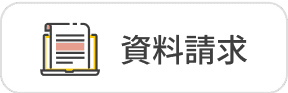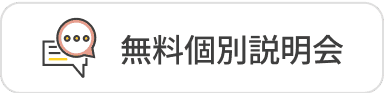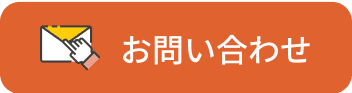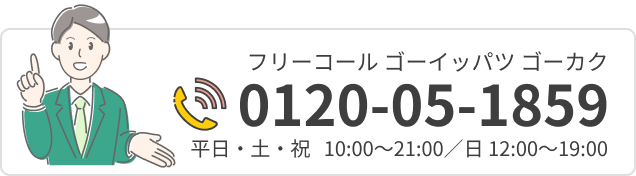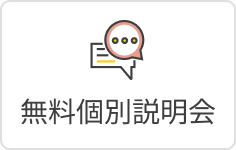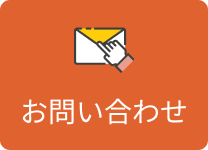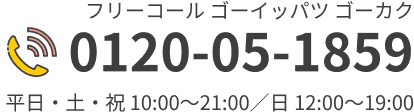newsロバみみ広場
アレコレつまみ食い国語-古典文法マスターへの道⑩-
音便変化について 動詞編
音便変化とは、発音で言いづらい言葉を言いやすく変えることです。音便は4種類あります。
イ音便(発音が「い」に変わる)
ウ音便(発音が「う」に変わる)
撥音便(発音が「ん」に変わる)
促音便(発音が「つ」に変わる)
重要なのは、音便変化している形をもとの形にきちんと戻せるかどうかです。もとに戻せないと誤読につながります。
音便変化するものはある程度限られるので、覚えてしまうとよいでしょう。
動詞の場合は、まず動詞の連用形に「て」「たり」が付いたとき、音便変化が起こります。
き・ぎ・しが「い」に変化
(例)書きて→書いて
ひ・び・みが「う」に変化
(例)言ひて→言うて
び・み・にが「ん」に変化
(例)呼びて→呼んで
4. ち・ひ・りが「つ」に変化
(例)折りて→折つて
もう1つ、頻出の公式は、ラ変動詞の連体形+終止形接続(ラ変型は連体形)の助動詞「なり・めり・べし」になるとき、撥音便化が起こります。
(例)あるなり→あんなり
さらにあんなりが省略されて「あなり」になることもあります。
次回は形容詞・形容動詞の音便変化の公式を説明します。
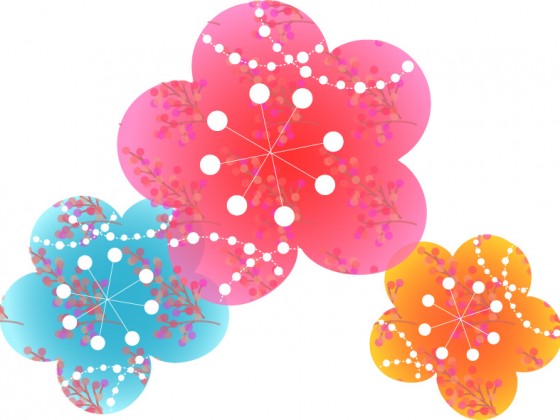



access 交通アクセス
access 交通アクセス
神泉駅(京王井の頭線)より徒歩2分
渋谷駅(JR各線、田園都市線、半蔵門線、銀座線、東横線、井の頭線)
より徒歩5分、渋谷マークシティ道玄坂出口より徒歩1分
渋谷マークシティ ウエストモール4F(レストランアベニュー)を通り、マークシティ「道玄坂出口」を出ます。
正面の「道玄坂上交番前」交差点の信号を渡り、左手へ上ります。
「道玄坂上交番」の前を過ぎ、20mほど進むと1Fに玉川屋呉服店がございます。そのビルの7Fがapsアカデミーです。
〒150-0044
東京都渋谷区円山町5-3 玉川屋ビル7F