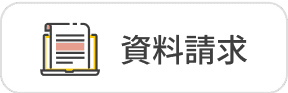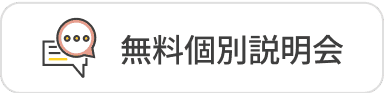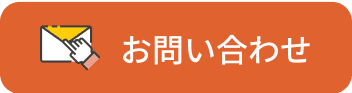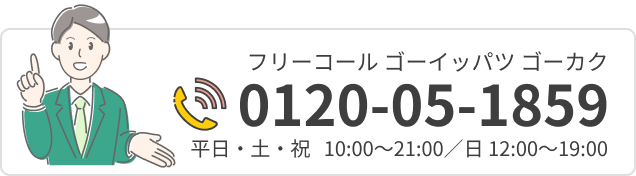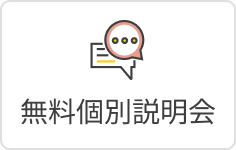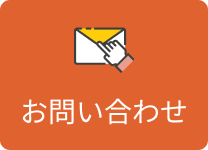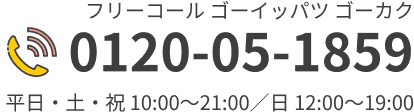newsロバみみ広場
アレコレつまみ食い国語‐古典文法の問題にチャレンジ!⑭<解説編 前編>‐
先週の問題↓
《問題》
助詞に注意しながら、その用法の正しい選択肢をそれぞれ選びなさい。
1 烏などもこそ見つくれ
2 身こそいやしけれ、心はさばかり下らんや
3 この殿の御心、さばかりにこそ。
イ 逆説
ロ 懸念
ハ 結びの省略
《解説》
係助詞といえば、係り結びが起きるというのは皆さんご存知だと思いますが
ほかにもいろいろな用法があります。
紛らわしいものもあるので、区別してしっかり理解しましょう。
①結びの省略
本来「こそ」が文中にあると文末は已然形になるが、ある一定の形をとるため文末の部分が省略されること。
(例)わが身の上は言ひにくくこそ。
→文末は省略されているので動詞「あり」の已然形「あれ」が本来は入る。
②結びの消滅
「こそ」の文末に値する箇所が、接続助詞につながることによってそちらの接続が優先され、已然形ではなくなること。
(例)たとひ耳鼻こそ切れ失すとも、・・・
→本来は「切れ失す」が「切れ失すれ」というように已然形になるはずだったが
接続助詞「とも」の接続が終止形なので、結びが消滅している。
③逆説の用法
「こそ~已然形、~」のように、係り結びで已然形になった部分が文末ではなく読点がおかれて文章が続く場合、その部分を接続助詞がなくても逆説(~けれども)と訳すこと。
(例)雨こそ止みしか、風なほやまず。
→本来は「しか」が文末に来るが、文章が続く場合は「~けれども」と訳すので
「雨は止んだけれど、風はまだ止まない」となる。
④懸念の用法
「こそ」の前に「も」という係助詞が付くことによって、「~すると困る・~すると大変だ」という懸念の訳し方をすること。
(例)からすもこそ見つくれ。
→本来「こそ」は強意の意味を持っていて訳に影響しないはずだが
「もこそ」の形になると「からすに見つかったら大変だ」という懸念の訳になる。
では問題の選択肢はどの用法にあてはまるでしょうか。
来週くわしく解説していきます。
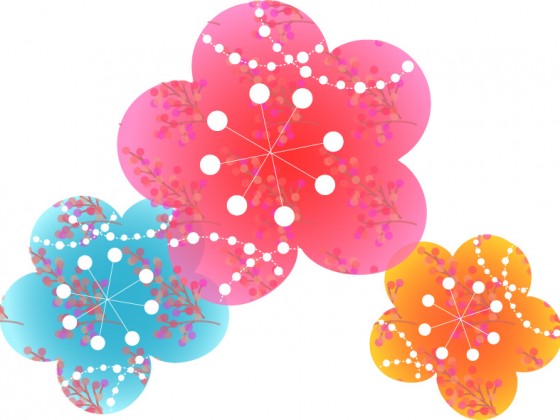



access 交通アクセス
access 交通アクセス
神泉駅(京王井の頭線)より徒歩2分
渋谷駅(JR各線、田園都市線、半蔵門線、銀座線、東横線、井の頭線)
より徒歩5分、渋谷マークシティ道玄坂出口より徒歩1分
渋谷マークシティ ウエストモール4F(レストランアベニュー)を通り、マークシティ「道玄坂出口」を出ます。
正面の「道玄坂上交番前」交差点の信号を渡り、左手へ上ります。
「道玄坂上交番」の前を過ぎ、20mほど進むと1Fに玉川屋呉服店がございます。そのビルの7Fがapsアカデミーです。
〒150-0044
東京都渋谷区円山町5-3 玉川屋ビル7F