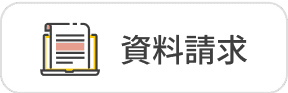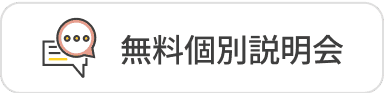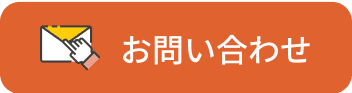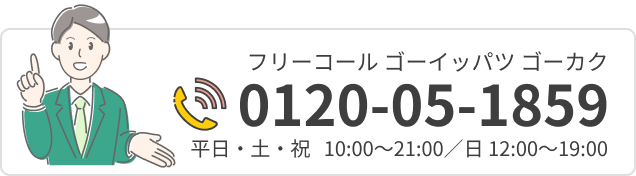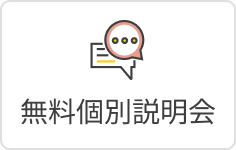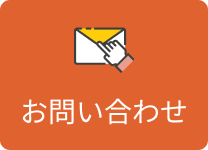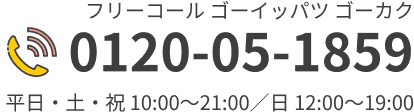newsロバみみ広場
アレコレつまみ食い国語‐古典文法の問題にチャレンジ!⑦<解説編>‐
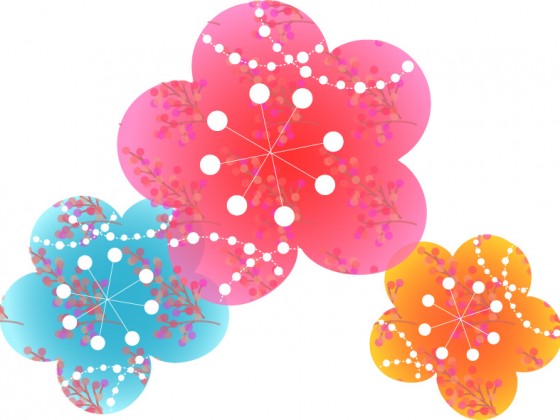
<問題>
大きなる柑子の木の、枝もたわゝになりたるが、まはりをきびしく囲ひたりしこそ、少しことさめて、「この木なからましかば」と覚えしか。
傍線部の文章を文末に省略してある部分を考えながら現代語訳しなさい。
解答・解説
助動詞「まし」の意味から見ていきましょう。
(ましかば・せば・未然形+ば~まし。の形で)反実仮想…もし~なら~だったのに
(疑問語を伴って)ためらいの意志…~しようかしら
「この木なからましかば」
この文章は「ましかば」が文末に来ています。反実仮想の文型は、「ましかば~まし。」と文末に「まし」が必ずくるはずです。
よって、ましかば。で終わっているということは、「~まし」の部分が省略されているということになります。
『大きなる柑子の木の、枝もたわゝになりたるが、まはりをきびしく囲ひたりしこそ、少しことさめて』
→大きい柑子の木で、枝もたわわになっている木が、周りを厳しく囲っていて、少し興ざめして
『「この木なからましかば」と覚えしか。』
→「この木がなかったならば…」と思った。
この「なかったならば」の後に続く言葉を考えましょう。
「ましかば」に省略されているのは「よからまし」(よかったのに)です。
柑子の木は実際にはある、でもなければよかったのに…という現実とは反対のことを仮想しています。(反実仮想)
もし文章が「ましかば」で終わっているものがあったら、「よからまし」を補ってあげましょう。
古文は省略が多い文学ですが、ある程度ルールを覚えて行けば正しく意味を解釈することができます。
答え→省略されている言葉「よからまし」
訳「この木がなかったならばよかったのに。」



access 交通アクセス
access 交通アクセス
神泉駅(京王井の頭線)より徒歩2分
渋谷駅(JR各線、田園都市線、半蔵門線、銀座線、東横線、井の頭線)
より徒歩5分、渋谷マークシティ道玄坂出口より徒歩1分
渋谷マークシティ ウエストモール4F(レストランアベニュー)を通り、マークシティ「道玄坂出口」を出ます。
正面の「道玄坂上交番前」交差点の信号を渡り、左手へ上ります。
「道玄坂上交番」の前を過ぎ、20mほど進むと1Fに玉川屋呉服店がございます。そのビルの7Fがapsアカデミーです。
〒150-0044
東京都渋谷区円山町5-3 玉川屋ビル7F