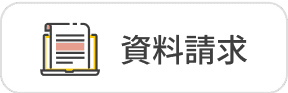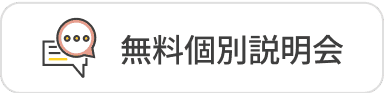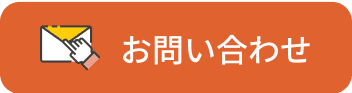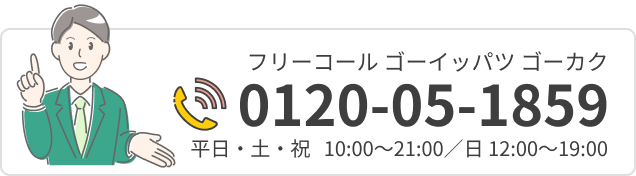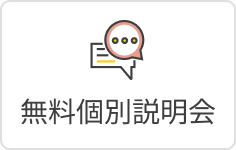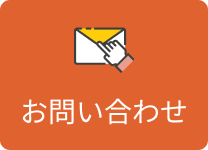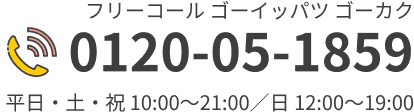newsロバみみ広場
受験英語教えて110番 No.111「believe ~ to」
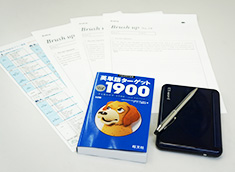
Q. ① I believe him to be honest.(私は彼が正直だと信じている)、② I believe him to know the fact.(私は彼がその事実を知っていると信じている)③ I believe him to go there.(私は彼がそこに行くと信じています) ①~③で①②はOKで③は×となる理由を教えてください。
解答・解説
A. ③が×ということですが、③も完全に×だということでもなく、あっても希なケースだということです。ただ、goの場合であれば次のようになるのが一般的です。
Ex.1 I believe that he will go there.
このようにthat節で表すのがベターだということです。これにはいくつか理由があるとは思いますが、それは後ほど説明することとして、まず確認しなければいけないことは、①のbe、②のknowがいわゆる「状態動詞」と言われるものだということです。この「状態動詞」がtoに後続する場合には、この構文<believe+[目的語]+to ~>が可能であるといえます。これはthinkやsupposeなども同じですが、「動作動詞」が来る場合にはthat節で表すのが一般的だということです。
さて③が不可である理由についてですが、これは私見も交えてお話しします。to の後ろに「動作動詞」と「状態動詞」がくる場合の決定的な違いは、to ~が表す時制に“曖昧さ”が残るかどうかということだと思います。to+「状態動詞」の場合には述語動詞と、この場合にはbelieveですが、to~の時制(①と②では現在形)が一致して、そこには“曖昧さ”がありません。しかし③のような「動作動詞」ではどうでしょう。時制的には未来と現在の二つの可能性がでてきてしまいます。例えば質問者は③を未来として訳していますが、現在形だと考えたらどうなるでしょう。つまり「私は彼がそこに通っていると信じています(習慣)」と訳すこともできるわけです。そこには“曖昧さ”が残ります。この「“曖昧さ”を避けるためにthat節をとる」と考えればすっきりしませんか。「動作動詞」でも次のようなケースは許されていることを併せて考えると、この論理が納得してもらえるのではないでしょうか。
Ex.2 I believe him to be going there.「私は彼がそこに向かっていると信じている」
Ex.3 I believe him to have gone there.「私は彼がそこに行ってしまっていると信じている」
上の英文のEx.2は現在の行為であり、Ex.3は過去の行為であることは明らかなのでthat 節で表さなくても、そこには時制の“曖昧さ”は存在しません。このことからも、< believe+[目的語]+to ~>でのtoに後続するものが「動作動詞」の場合、時制の“曖昧さ” が存在する限りにおいては避けるべきだということではないでしょうか。自説も交えての 説明ではありますが、何か参考になればと思います。



access 交通アクセス
access 交通アクセス
神泉駅(京王井の頭線)より徒歩2分
渋谷駅(JR各線、田園都市線、半蔵門線、銀座線、東横線、井の頭線)
より徒歩5分、渋谷マークシティ道玄坂出口より徒歩1分
渋谷マークシティ ウエストモール4F(レストランアベニュー)を通り、マークシティ「道玄坂出口」を出ます。
正面の「道玄坂上交番前」交差点の信号を渡り、左手へ上ります。
「道玄坂上交番」の前を過ぎ、20mほど進むと1Fに玉川屋呉服店がございます。そのビルの7Fがapsアカデミーです。
〒150-0044
東京都渋谷区円山町5-3 玉川屋ビル7F